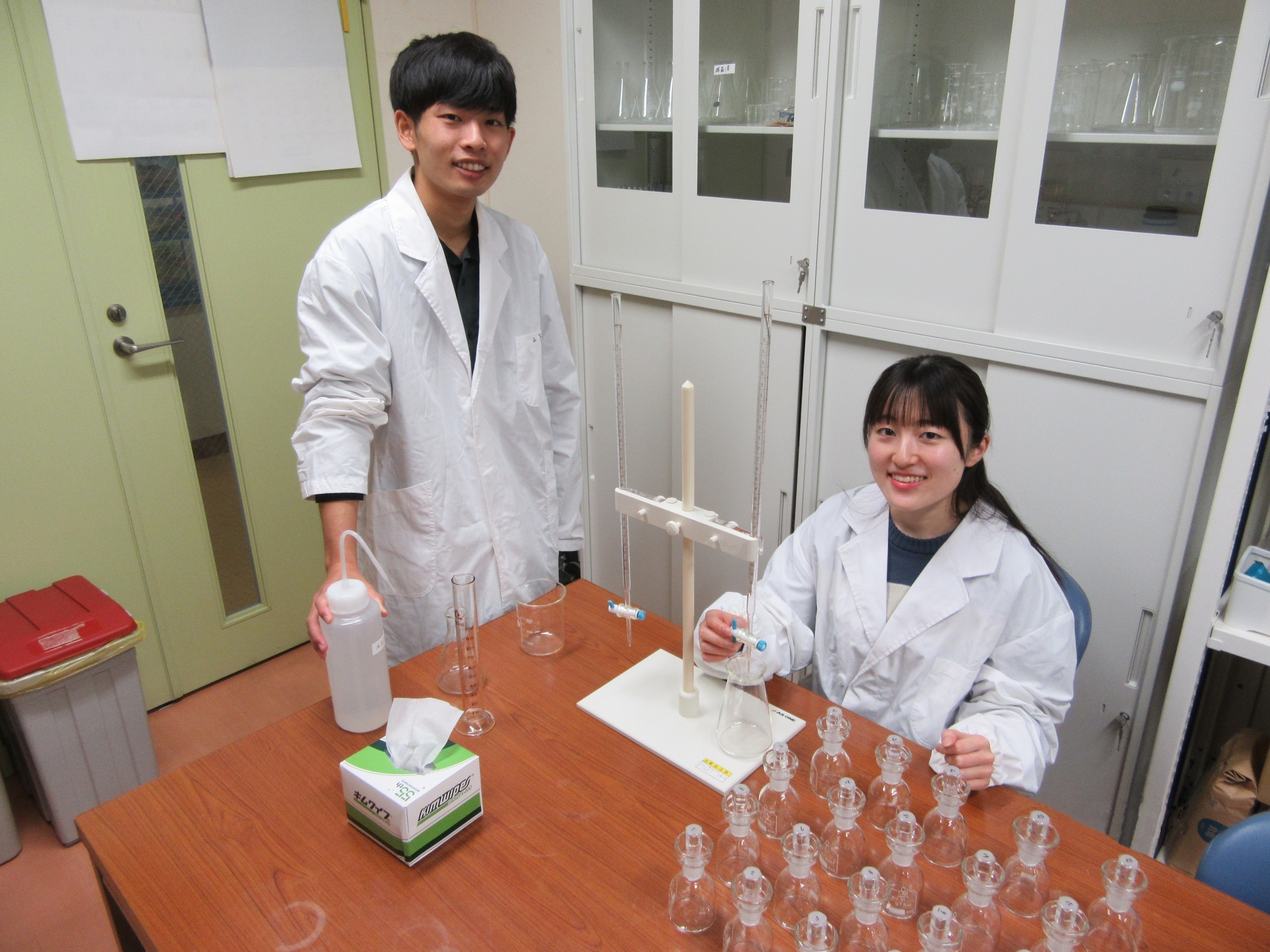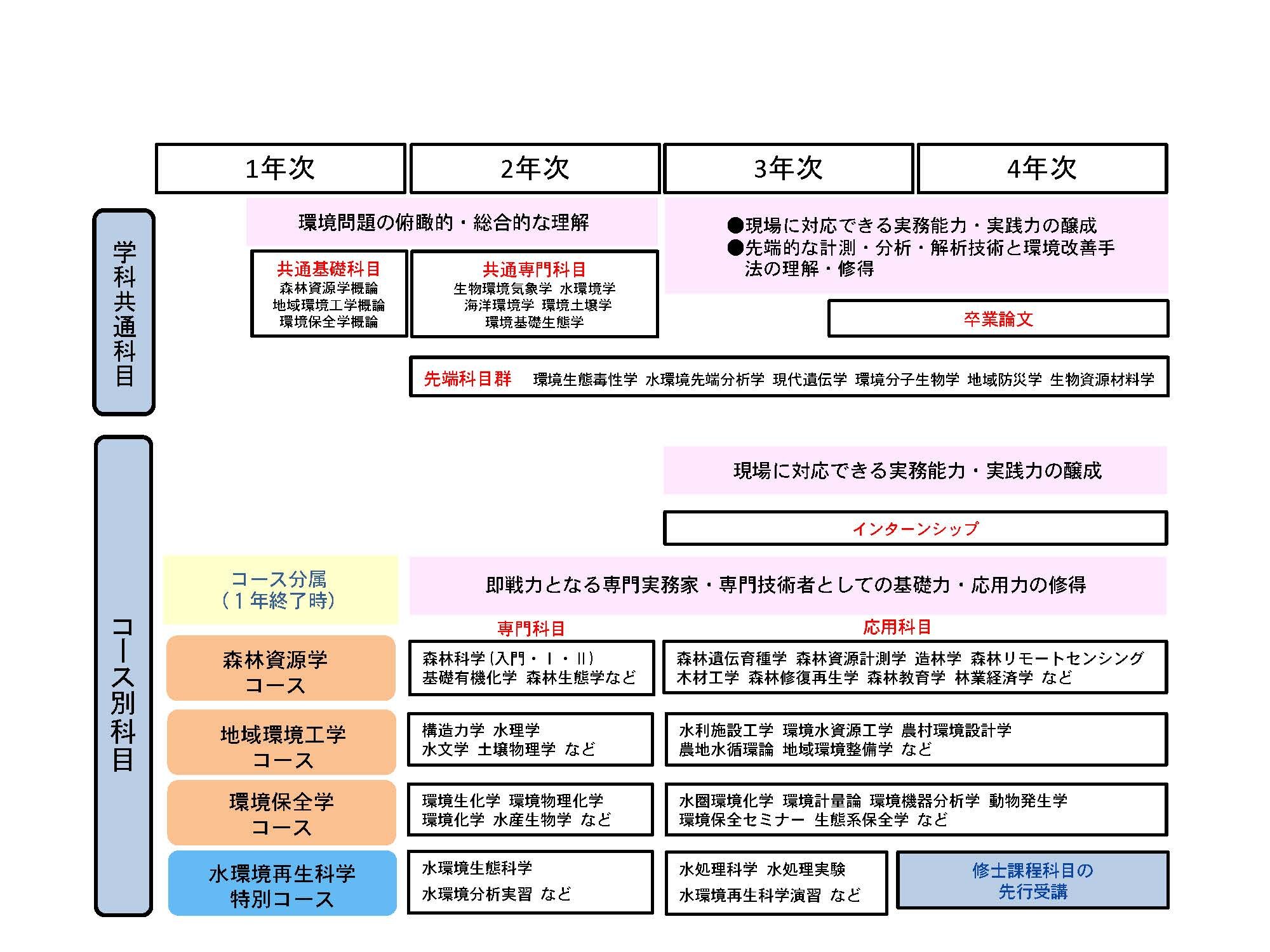生物環境学科は、山から海に至る広範囲の環境に関する様々な問題を解決するための俯瞰的な視野をもち、地域規模から世界規模の範囲で活躍する意欲のある学生を求めます。そのため、一般選抜に加えて、学校推薦型選抜や総合型選抜などの様々な入試方法も採用しています。
そこで、生物環境学科は次のような資質を有する学生を求めます。
-
思考・判断
ある事象に対して多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
-
興味・関心・意欲
地域社会や国際社会における食料、生命、環境に関する様々な問題に関心をもち、身に付けた知識をこれらの解決に役立てたいという意欲をもっている。
-
表現
自分の考えを、日本語で他者にもわかりやすく表現できる。
-
主体性・協働性
問題解決のために、主体性をもって多様な人々と協力できる。
選考方法の趣旨
【一般選抜 前期日程】
大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力をみるために、6教科8科目を課し、「知識・技能・理解」を評価します。また、個別学力試験では、数学と理科1科目を課し、「思考・判断」、「表現」を評価します。さらに、調査書により、「主体性・協働性」を評価します。
【一般選抜 後期日程】
大学入学共通テストでは、入学後の修学に必要な高等学校レベルでの幅広い分野の基礎学力をみるために、6教科8科目を課し、「知識・技能・理解」を評価します。また、面接試験では、生物環境に関連する様々な問題への「関心」度、問題解決に向けた「意欲」、それに対する「思考・判断」、「表現」、「主体性・協働性」を評価します。さらに、調査書により、「主体性・協働性」を評価します。
【学校推薦型選抜ⅠA】
国語、英語、理科・数学系の3教科からなる総合問題により、高等学校等で修得する「知識・技能・理解」と「思考・判断」力を評価します。また、面接(口頭試問を含む。)により、高等学校等で履修する教科・科目についての基礎的な知識、生物環境に関する様々な問題への関心とこれらの問題への解決意欲、自分の考えをまとめ、表現する力を有しているかを評価します。さらに、面接と調査書・活動報告書により、「主体性・協働性」を評価します。
【学校推薦型選抜ⅠB】
国語、英語、理科・数学系の3教科からなる総合問題により、高等学校等で修得する「知識・技能・理解」と「思考・判断」力を評価します。また、面接(口頭試問を含む。)により、高等学校等で履修する教科・科目についての基礎的な知識、生物環境に関する様々な問題への関心とこれらの問題への解決意欲、自分の考えをまとめ、表現する力を有しているかを評価します。なお、「専門教育を主とする学科」からの受験者には森林、農業土木、環境などに関する専門的な知識・技術を有しているかを、「総合学科」からの受験者には高等学校等で選択履修した教科・科目について実践的・体験的学習から得られた知識・技術を有しているかを、面接(口頭試問を含む。)の中で評価します。さらに、面接と調査書・活動報告書により、「主体性・協働性」を評価します。