メッセージ

愛媛大学農学部は、1900年に設立された愛媛県農業学校から始まる120年以上の長い歴史を持つ農学部です。そして、1967年には、さらに高度な教育研究を行うための大学院農学研究科が設置され、地域と世界の農林水産業および農学の発展に貢献する沢山の有能な卒業生、修了生を育成、輩出してまいりました。
現在の愛媛大学農学部・農学研究科は、地域と世界の益々の発展のために「自然と共生する持続可能な社会を構築する」ことを大きな目標として掲げ、「食料・生命・環境」をキーワードとした3学科体制で、教育研究そして社会貢献活動を活発に進めています。また、愛媛大学農学部・農学研究科は、中国四国地域で有数の規模の農学部・農学研究科であるため、幅広い農学分野の、ほぼ全ての内容をカバーした高度な教育研究を行っていることも特色の一つです。それゆえ、近年話題とされることが多い「SDGs、DX、カーボンニュートラル、レジリエント、スマート農業」といった現代のキーワードに対しても、的確に対応した先端的かつ実用的な多彩な教育研究を展開しています。
愛媛大学農学部・農学研究科は、松山市の樽味地区という、松山市の中心街から約2.5km程度の距離にあり、生活の利便性を持ちながらも、閑静な住宅地が広がる落ち着いた環境の中にあります。このような、快適で充実した環境の下で、皆さんとともに、新しい社会を築き、発展させる素晴らしい教育研究と社会貢献活動を、これからも活発に進めていきたいと考えています。
農学部長・大学院農学研究科長 治多 伸介
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
教育理念と教育目的
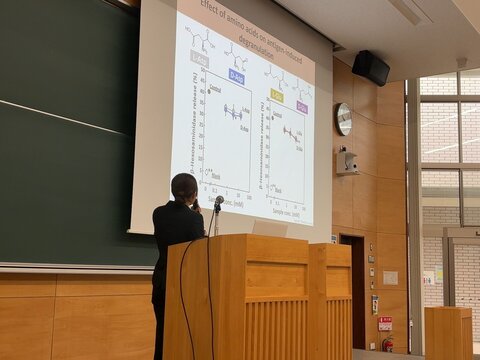 農学部は、愛媛大学学則及び愛媛大学憲章の趣旨を踏まえ、生物生産技術の開発と安全・安心な食料の安定供給、生命機能の解明と生物資源の利用、生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関する専門知識・技術を修得させ、地域的な視点と国際的な視野から食料、生命、環境に関する様々な問題を解決し、自然と共生する持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成することを教育理念とします。また、農学領域における様々な研究及びそれらの成果を基に、食料、生命、環境に関する専門的知識・技術を学生に修得させ、自然と人間が調和する循環型社会の創造に貢献できる専門職業人や技術者を養成することによって、地域社会や国際社会における産業の発展と文化の進展に貢献することを目的としています。
農学部は、愛媛大学学則及び愛媛大学憲章の趣旨を踏まえ、生物生産技術の開発と安全・安心な食料の安定供給、生命機能の解明と生物資源の利用、生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関する専門知識・技術を修得させ、地域的な視点と国際的な視野から食料、生命、環境に関する様々な問題を解決し、自然と共生する持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成することを教育理念とします。また、農学領域における様々な研究及びそれらの成果を基に、食料、生命、環境に関する専門的知識・技術を学生に修得させ、自然と人間が調和する循環型社会の創造に貢献できる専門職業人や技術者を養成することによって、地域社会や国際社会における産業の発展と文化の進展に貢献することを目的としています。
育成する人材像
愛媛大学の基本理念に基づいて、「学生中心の大学」として学生の多様な志向性を尊重した農学教育を提供することにより、生物生産技術の開発と安全・安心な食料の安定供給、生命機能の解明と生物資源の利用、生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関する様々な問題を解決し、自然と共生する持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成します。
学習の到達目標
-
知識・技能・理解
生物生産技術の開発と安全・安心な食料の安定供給、生命機能の解明と生物資源の利用、生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関するいずれかの専門知識と技術を身に付けている。
-
思考・判断
地域社会や国際社会における食料、生命、環境に関連する諸課題の原因を論理的に説明でき、解決策を見出すことができる。
-
興味・関心・意欲
上記の諸課題への関心と身に付けた知識をこれらの解決に役立てたいという意欲をもち、倫理性をもって、継続的に課題解決のための行動をとることができる。
-
表現
自らの論理的な思考・判断のプロセスや結果を説明するためのプレゼンテーション能力とコミュニケーション能力を有している。
-
主体性・協働性
主体性をもって多様な人々と協力することにより、上記諸課題の解決に取り組むことができる。
卒業認定・学位授与
農学部規則に定められた単位数を修得した学生に対して、卒業を認定し学士(農学)の学位を授与します。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
教育課程の編成と教育内容
農学部では、基礎となる学習から専門知識と技術の修得までを段階的に学べるカリキュラムを編成しています。本カリキュラムは、全学共通教育科目、学部共通科目、学科共通科目及びコース専門科目から構成されています。1年次は、全学共通教育科目に加え、農学を構成する食料、生命、環境に関する広範で俯瞰的な知識と技術を修得するための学部共通科目、各学科の基礎知識を修得するための学科共通科目を開講しています。2 年次よりコースに分属し、専門知識と技術を修得するためのコース専門科目を開講しています。さらに、卒業論文の開始時期を3 年次とし、修得した専門知識や技術に基づいて卒業論文に取り組むことで論理的思考と課題解決能力、さらに未来を創造するデザイン能力を身に付けます。
教育方法と成績評価
講義形式の授業だけでなく、実験・実習等のアクティブ・ラーニングなど、ディプロマ・ポリシーに示す教育目的と学習の到達目標に応じて最適な形式の授業を実施します。また、授業時間外の学習を含む十分な学習時間を確保できるように履修登録制限(CAP制)を設けるとともに、eラーニングなど時間外学習を支援するツールを用意します。
すべての授業において、客観的な評価基準に基づき、筆記試験、レポートなどにより厳格な成績評価を実施します。
カリキュラムの評価
授業アンケート、入学者アンケート、卒業予定者アンケートなどの学生調査と各種統計データの分析を実施し、個々の授業科目の教育効果や、農学部の学修到達目標の達成状況について検証します。
アドミッション・ポリシー(入学者受入の方針)
農学部は、生物生産技術の開発と安全・安心な食料の安定供給、生命機能の解明と生物資源の利用、生物環境の創造・修復・保全・管理・利用に関する様々な問題を解決し、自然と共生する持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成することを教育理念としています。この教育理念に基づき、地域社会や国際社会における食料、生命、環境に関する様々な問題の解決に熱意をもち、主体性と多様な能力をもった学生を求めます。そのため、一般選抜に加えて、学校推薦型選抜や総合型選抜などの様々な入試方法も採用しています。
そこで、農学部は次のような資質を有する学生を求めます。
-
知識・技能・理解
1.入学後の修学に必要な基礎学力を有している。
2.次のいずれかに該当する。
(1)[一般選抜、総合型選抜Ⅱ]
高等学校等で履修する6教科(国語、数学、理科、地理歴史・公民、外国語、情報)の基礎的な知識・技能を有している。
(2)[学校推薦型選抜ⅠA]
高等学校等で履修する国語、英語、理科・数学系の基礎的な知識・技能を有している。
(3)[学校推薦型選抜ⅠB]
高等学校等で履修する国語、英語、理科・数学系の基礎的な知識・技能を有し、農林水産業、工業、商業などに関する専門的な知識・技術を有しているか、高等学校等で選択履修した教科・科目について実践的・体験的学習から得られた知識・技術を有している。
-
思考・判断
ある事象に対して多面的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
-
興味・関心・意欲
地域社会や国際社会における食料、生命、環境に関する様々な問題に関心をもち、身に付けた知識をこれらの解決に役立てたいという意欲をもっている。
-
表現
自分の考えを、日本語で他者にもわかりやすく表現できる。
-
主体性・協働性
問題解決のために、主体性をもって多様な人々と協力できる。

