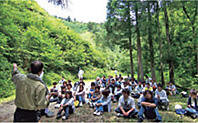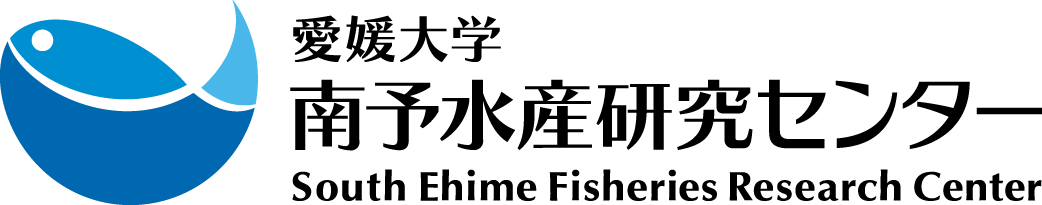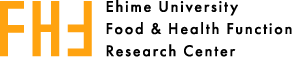附属施設
-
農学部附属農場

農場風景 
農学部附属農場は、瀬戸内海に面した高縄山系の緩やかな傾斜地に位置しており、研究・管理棟を始め、温室、収納作業室、加工室、畜舎などの建物・施設と水田、畑、果樹園、草地が配置されています。ここでは、作物の栽培管理や調理実習などを体験することによって、その作物を育む自然のあり方、農のあり方、食のあり方などをさまざまなことに思いを深めることのできる学生の実習教育を行うとともに、農学の諸理論を活用して生産現場で活かすことのできる技術開発に取り組んでいます。また、近隣の耕作放棄地を利用した減農薬米の生産や、次代を担う子供達の体験学習の場としてみかん狩り、家畜とのふれあい、1泊2日の「子ども農業体験教室」などを実施して、地域振興や地域との連携に力を注いでいます。
-
農学部附属演習林
農学部附属演習林の米野々森林研究センター(農学部の北東約18Km)は、演習林管理機能及び教育研究機能を備えた研究棟と、実験林(面積384ha)とで構成される教育研究施設です。本施設では、森林を対象とする多分野にわたる試験研究と、森林科学に関する実習を中心に実践教育が行われています。また、公開講座などをとおして、大学で培った教育研究の成果を広く地域社会に還元する取組を積極的に展開しています。
-
久万高原キャンパス
久万高原キャンパスは、2022年4月に大学院森林環境管理特別コースおよび森林環境管理リカレントコース(いずれも現在は廃止)による環境に配慮した森林管理や資源利用が行える高度な技術を有した専門的な人材を育成するために、愛媛県林業研究センターの展示研修館内をお借りするかたちで開校しました。現在は、後継の「森林環境管理学リカレントプログラム」にて森林を未来に繋ぐ社会資本として森林を育て、管理する知識や視角を持った地域の森林環境管理のキーパーソンを育成する拠点として活用しています。
-
大学院農学研究科附属環境先端技術センター
当施設では環境の時代を担う新しい学術研究分野として環境と持続的発展を目指す産業とを結びつける循環型環境創造研究を展開し、地域社会との連携を積極的に推し進めています。特に現在は、新規環境汚染物質の検出システムの開発、有害化学物質の浄化技術及び廃棄物の有用資源化技術開発、各種バイオマスエネルギー資源化に関する研究等に取り組んでいます。
-
大学院農学研究科柑橘産業イノベーションセンター
愛媛県の主要産業である柑橘産業は、「平成30年7月豪雨」により愛媛県内各地で甚大な被害を受け、特に、「愛媛みかん発祥の地」として知られ、200年以上のみかん栽培の歴史のある宇和島市吉田町、及び、西予市の被害は特に深刻でした。農学研究科では、愛媛県内の柑橘産業の復興と発展を支援するため、予てから愛媛県内のステークホルダーからの要望もあり懸案であった、柑橘産業に関する研究・人材育成等の拠点を設置することといたしました。 農学研究科における研究分野は多岐に及び、これまでに培ってきた栽培技術、遺伝子研究、園地管理、食品、流通、経営、防災等の幅広いシーズを最大限に利用して、柑橘産業における様々な課題に対応していきます。また、愛媛大学防災情報研究センター、愛媛大学食品健康機能研究センター、愛媛県農林水産研究所との連携を図り、将来の災害に備えるシステムの構築や生産振興に資する活動を通し、愛媛県内の柑橘産業の発展を支援する地域産業特化型研究センターを目指します。
-
大学院農学研究科ハダカムギ開発研究センター
ハダカムギ開発研究センターは、愛媛県の主要農産物である裸麦の生産振興と需要拡大に貢献することを目的に松山市東方町に設置しました。 当センターでは品種開発のための遺伝資源コレクションの開発、遺伝資源情報の整備および優良形質のテーラーメイドによる導入と育種、品種開発のための生産性・品質の評価、栽培技術の高度化、超高齢化社会に資する裸麦の機能性の探索と解析、地域企業・団体と連携による機能性を生かした商品の開発と新たな利用法の提案、地域食文化の継承・発展に関わる地域人材の育成に取り組んでいます。
関連施設
-
愛媛大学 南予水産研究センター
南予水産研究センターは、日本の水産養殖のメッカである愛媛県愛南町に位置しており、海洋生物の飼育および分子・細胞レベルでの解析ができる施設・設備を整備しています。ここでは、水産業を生命科学、環境科学および社会科学の視点から海洋生物資源の利用、海洋での生物生産技術の開発、更には地域漁業の活性化を目指した教育研究を行っています。水産業の盛んなフィールドの特性を活かし、地域の漁業者との連携を重視した実践型の教育研究を行っています。
-
愛媛大学 先端農業R&Dセンター
我が国の農業は、農業の担い手の減少と超高齢化、これに伴って食料自給率は極めて低い状態が続いており、従来の生産方式を前提とした農業生産では、農業の持続的な発展や食料の安定供給が確保できなくなっています。本センターは、植物工場に係わる研究で蓄積してきた技術開発力や人的ネットワークを活用して、植物工場システムの知能化を一層進めるとともに、食料生産全体のスマート化及びアグリカーボンニュートラルを実現し、加えて、先端農業に必要な技術を修得した人材を育成することで、食料生産の一層の高度化に貢献することを目的としています。これらの教育研究活動を産・官・学が連携して実施し、実用に繋がる学術研究の振興と研究成果の地域社会への活用を推進しています。
-
愛媛大学 紙産業イノベーションセンター
紙産業イノベーションセンターは、紙産業に関する学際的な研究及び教育を行うことにより、紙産業の発展につながる研究開発の推進と地域社会の活性化に貢献することを目的に、日本一の紙の町である四国中央市に設置しました。 ここでは、製紙・紙加工に関する課題解決と製紙技術の高度化に向けた研究や、機能性材料等の紙への付与による新規紙製品の開発を行っています。また、新技術の実用化を推進するために、企業との調整や特許案件の整理等を行う「地域連携・研究支援室」を設置して、産業界への速やかな研究成果の還元を目指しています。紙産業の盛んな地域の特徴を活かし、ステークホルダーと連携しながら、実践型の研究・教育を行っています。
-
愛媛大学 食品健康機能研究センター
食品健康機能研究センターは、食と健康に関する研究の発展及び産学官連携による食品の開発に貢献し、国内外を問わず広い地域へと研究を展開し、地域産業の活性化及び国民の健康増進に寄与することを目的として、令和5年7月1日に設置されました。本センターでは①機能性食品の開発、②栄養疫学研究の社会実装、③個々人の健康に寄り添った情報発信による健康長寿社会の実現、④食品機能学研究の国際展開と社会実装を推進し、食品化学領域の研究力及び人材育成機能の高度化、拡大する地域ニーズへの柔軟な対応、海外への展開、さらには地域産業の活性化や起業促進といった本学の地域連携機能を一層強化していきます。
-
愛媛大学 沿岸環境科学研究センター
沿岸環境科学研究センター(CMES)は、物理学、化学、生物学等を基礎とする3つの研究部門と国際・社会連携室で構成され、沿岸域の環境や生態系の研究、外洋や陸域も含めた広汎な化学汚染と毒性影響の研究、ヒト・動物・環境の健康を包括的に守るワンヘルス研究を、学際的、総合的に推進しています。海洋調査には、調査・実習船「いさな」(14t)が活躍しています。また、世界各地から採取した野生生物や土壌などの試料を保存・管理し、学内外の研究に提供するための「生物環境試料バンク」も備えています。また、センターが母体となる共同利用・共同研究拠点「化学汚染・沿岸環境研究拠点(LaMer)」が平成28年と令和4年に文部科学省の認定を受け、国内外の研究拠点としても活動しています。
-
愛媛大学 学術支援センター 遺伝子解析部門
DNAの塩基配列解析、タンパク質の構造機能解析など遺伝子に関する教育研究、放射性同位元素を扱う教育研究を支援します。P2、P3レベルの遺伝子組換え実験に対応する設備を有し、特にP3レベル実験室は愛媛県内で唯一の施設です。トレーサー実験などが行える放射性同位元素実験室や測定室を併設しています。動物飼育室、植物、微生物の培養室を有し、一般的な生物材料を取り扱った実験を行うことも可能です。農学部をはじめとして、学内外の多くの教育研究を支援しています。また、毎年8月には、高校生を対象に遺伝子組換え実験の公開講座を開催しています。
-
愛媛大学 総合情報メディアセンター 農学部分室
総合情報メディアセンター農学部分室は城北キャンパスと同様の情報教育環境を整備しています。学生は入学時に発行するアカウントを使用し、授業以外にも、レポート作成、インターネット検索、電子メール等にパソコン(53台)を利用できます。 農学部におけるネットワーク環境の整備も行っています。情報セキュリティ対策に力を入れており、安心して教育・研究にインターネットを利用することができるよう努めています。講義室では愛媛大学無線ネットワークを利用可能としており、モバイル端末を使用した教育に対応しています。
-
愛媛大学 図書館 農学部分館
農学部分館には、開架図書コーナー、参考図書コーナー、新着雑誌コーナー、留学生コーナー、グループ学習室、書庫などがあり、141席の閲覧席、AV機器3台、蔵書検索端末(OPAC)1台を設置しております。 開館時間は、平日が午前9時から午後8時、土曜日(夏季・冬季休業期間を除く)は午前9時から午後1時までです。日曜・祝日・年末年始は閉館となります。
附属関連施設
-
農学部附属農場

農場風景 
農学部附属農場は、瀬戸内海に面した高縄山系の緩やかな傾斜地に位置しており、研究・管理棟を始め、温室、収納作業室、加工室、畜舎などの建物・施設と水田、畑、果樹園、草地が配置されています。ここでは、作物の栽培管理や調理実習などを体験することによって、その作物を育む自然のあり方、農のあり方、食のあり方などをさまざまなことに思いを深めることのできる学生の実習教育を行うとともに、農学の諸理論を活用して生産現場で活かすことのできる技術開発に取り組んでいます。また、近隣の耕作放棄地を利用した減農薬米の生産や、次代を担う子供達の体験学習の場としてみかん狩り、家畜とのふれあい、1泊2日の「子ども農業体験教室」などを実施して、地域振興や地域との連携に力を注いでいます。
-
農学部附属演習林
農学部附属演習林の米野々森林研究センター(農学部の北東約18Km)は、演習林管理機能及び教育研究機能を備えた研究棟と、実験林(面積384ha)とで構成される教育研究施設です。本施設では、森林を対象とする多分野にわたる試験研究と、森林科学に関する実習を中心に実践教育が行われています。また、公開講座などをとおして、大学で培った教育研究の成果を広く地域社会に還元する取組を積極的に展開しています。
-
久万高原キャンパス
久万高原キャンパスは、2022年4月に大学院森林環境管理特別コースおよび森林環境管理リカレントコース(いずれも現在は廃止)による環境に配慮した森林管理や資源利用が行える高度な技術を有した専門的な人材を育成するために、愛媛県林業研究センターの展示研修館内をお借りするかたちで開校しました。現在は、後継の「森林環境管理学リカレントプログラム」にて森林を未来に繋ぐ社会資本として森林を育て、管理する知識や視角を持った地域の森林環境管理のキーパーソンを育成する拠点として活用しています。
-
大学院農学研究科附属環境先端技術センター
当施設では環境の時代を担う新しい学術研究分野として環境と持続的発展を目指す産業とを結びつける循環型環境創造研究を展開し、地域社会との連携を積極的に推し進めています。特に現在は、新規環境汚染物質の検出システムの開発、有害化学物質の浄化技術及び廃棄物の有用資源化技術開発、各種バイオマスエネルギー資源化に関する研究等に取り組んでいます。
-
大学院農学研究科柑橘産業イノベーションセンター
愛媛県の主要産業である柑橘産業は、「平成30年7月豪雨」により愛媛県内各地で甚大な被害を受け、特に、「愛媛みかん発祥の地」として知られ、200年以上のみかん栽培の歴史のある宇和島市吉田町、及び、西予市の被害は特に深刻でした。農学研究科では、愛媛県内の柑橘産業の復興と発展を支援するため、予てから愛媛県内のステークホルダーからの要望もあり懸案であった、柑橘産業に関する研究・人材育成等の拠点を設置することといたしました。 農学研究科における研究分野は多岐に及び、これまでに培ってきた栽培技術、遺伝子研究、園地管理、食品、流通、経営、防災等の幅広いシーズを最大限に利用して、柑橘産業における様々な課題に対応していきます。また、愛媛大学防災情報研究センター、愛媛大学食品健康機能研究センター、愛媛県農林水産研究所との連携を図り、将来の災害に備えるシステムの構築や生産振興に資する活動を通し、愛媛県内の柑橘産業の発展を支援する地域産業特化型研究センターを目指します。
-
大学院農学研究科ハダカムギ開発研究センター
ハダカムギ開発研究センターは、愛媛県の主要農産物である裸麦の生産振興と需要拡大に貢献することを目的に松山市東方町に設置しました。 当センターでは品種開発のための遺伝資源コレクションの開発、遺伝資源情報の整備および優良形質のテーラーメイドによる導入と育種、品種開発のための生産性・品質の評価、栽培技術の高度化、超高齢化社会に資する裸麦の機能性の探索と解析、地域企業・団体と連携による機能性を生かした商品の開発と新たな利用法の提案、地域食文化の継承・発展に関わる地域人材の育成に取り組んでいます。
関連施設
-
愛媛大学 南予水産研究センター
南予水産研究センターは、日本の水産養殖のメッカである愛媛県愛南町に位置しており、海洋生物の飼育および分子・細胞レベルでの解析ができる施設・設備を整備しています。ここでは、水産業を生命科学、環境科学および社会科学の視点から海洋生物資源の利用、海洋での生物生産技術の開発、更には地域漁業の活性化を目指した教育研究を行っています。水産業の盛んなフィールドの特性を活かし、地域の漁業者との連携を重視した実践型の教育研究を行っています。
-
愛媛大学 先端農業R&Dセンター
我が国の農業は、農業の担い手の減少と超高齢化、これに伴って食料自給率は極めて低い状態が続いており、従来の生産方式を前提とした農業生産では、農業の持続的な発展や食料の安定供給が確保できなくなっています。本センターは、植物工場に係わる研究で蓄積してきた技術開発力や人的ネットワークを活用して、植物工場システムの知能化を一層進めるとともに、食料生産全体のスマート化及びアグリカーボンニュートラルを実現し、加えて、先端農業に必要な技術を修得した人材を育成することで、食料生産の一層の高度化に貢献することを目的としています。これらの教育研究活動を産・官・学が連携して実施し、実用に繋がる学術研究の振興と研究成果の地域社会への活用を推進しています。
-
愛媛大学 紙産業イノベーションセンター
紙産業イノベーションセンターは、紙産業に関する学際的な研究及び教育を行うことにより、紙産業の発展につながる研究開発の推進と地域社会の活性化に貢献することを目的に、日本一の紙の町である四国中央市に設置しました。 ここでは、製紙・紙加工に関する課題解決と製紙技術の高度化に向けた研究や、機能性材料等の紙への付与による新規紙製品の開発を行っています。また、新技術の実用化を推進するために、企業との調整や特許案件の整理等を行う「地域連携・研究支援室」を設置して、産業界への速やかな研究成果の還元を目指しています。紙産業の盛んな地域の特徴を活かし、ステークホルダーと連携しながら、実践型の研究・教育を行っています。
-
愛媛大学 食品健康機能研究センター
食品健康機能研究センターは、食と健康に関する研究の発展及び産学官連携による食品の開発に貢献し、国内外を問わず広い地域へと研究を展開し、地域産業の活性化及び国民の健康増進に寄与することを目的として、令和5年7月1日に設置されました。本センターでは①機能性食品の開発、②栄養疫学研究の社会実装、③個々人の健康に寄り添った情報発信による健康長寿社会の実現、④食品機能学研究の国際展開と社会実装を推進し、食品化学領域の研究力及び人材育成機能の高度化、拡大する地域ニーズへの柔軟な対応、海外への展開、さらには地域産業の活性化や起業促進といった本学の地域連携機能を一層強化していきます。
-
愛媛大学 沿岸環境科学研究センター
沿岸環境科学研究センター(CMES)は、物理学、化学、生物学等を基礎とする3つの研究部門と国際・社会連携室で構成され、沿岸域の環境や生態系の研究、外洋や陸域も含めた広汎な化学汚染と毒性影響の研究、ヒト・動物・環境の健康を包括的に守るワンヘルス研究を、学際的、総合的に推進しています。海洋調査には、調査・実習船「いさな」(14t)が活躍しています。また、世界各地から採取した野生生物や土壌などの試料を保存・管理し、学内外の研究に提供するための「生物環境試料バンク」も備えています。また、センターが母体となる共同利用・共同研究拠点「化学汚染・沿岸環境研究拠点(LaMer)」が平成28年と令和4年に文部科学省の認定を受け、国内外の研究拠点としても活動しています。
-
愛媛大学 学術支援センター 遺伝子解析部門
DNAの塩基配列解析、タンパク質の構造機能解析など遺伝子に関する教育研究、放射性同位元素を扱う教育研究を支援します。P2、P3レベルの遺伝子組換え実験に対応する設備を有し、特にP3レベル実験室は愛媛県内で唯一の施設です。トレーサー実験などが行える放射性同位元素実験室や測定室を併設しています。動物飼育室、植物、微生物の培養室を有し、一般的な生物材料を取り扱った実験を行うことも可能です。農学部をはじめとして、学内外の多くの教育研究を支援しています。また、毎年8月には、高校生を対象に遺伝子組換え実験の公開講座を開催しています。
-
愛媛大学 総合情報メディアセンター 農学部分室
総合情報メディアセンター農学部分室は城北キャンパスと同様の情報教育環境を整備しています。学生は入学時に発行するアカウントを使用し、授業以外にも、レポート作成、インターネット検索、電子メール等にパソコン(53台)を利用できます。 農学部におけるネットワーク環境の整備も行っています。情報セキュリティ対策に力を入れており、安心して教育・研究にインターネットを利用することができるよう努めています。講義室では愛媛大学無線ネットワークを利用可能としており、モバイル端末を使用した教育に対応しています。
-
愛媛大学 図書館 農学部分館
農学部分館には、開架図書コーナー、参考図書コーナー、新着雑誌コーナー、留学生コーナー、グループ学習室、書庫などがあり、141席の閲覧席、AV機器3台、蔵書検索端末(OPAC)1台を設置しております。 開館時間は、平日が午前9時から午後8時、土曜日(夏季・冬季休業期間を除く)は午前9時から午後1時までです。日曜・祝日・年末年始は閉館となります。